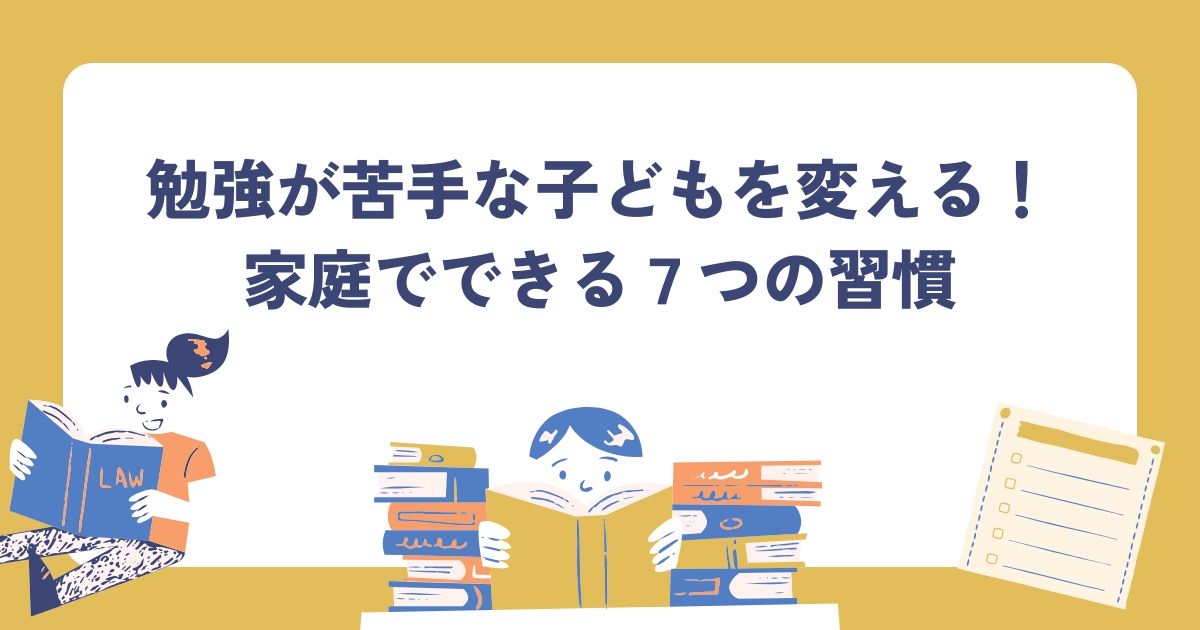「勉強が苦手な子どもが宿題を全然やらない」
「勉強が苦手になり成績が下がった」
「勉強が苦手な子どもにどう声をかければいいのかわからない」
勉強が苦手な子どもへの対応に悩む家庭は多いです。
勉強が苦手な子のやる気を出すには、家庭での声かけや学習習慣づくりが大切です。
この記事では、勉強が苦手な子どもが少しずつ机に向かえるようになる家庭でできる7つの習慣をご紹介します。
勉強が苦手な子どもに共通する特徴は?
 勉強が苦手な子どもには、いくつかの共通した特徴があります。
勉強が苦手な子どもには、いくつかの共通した特徴があります。
心理的な要因や家庭環境、学年が上がり学習内容が難しくなるなど、複数の要素が重なっているケースが多いです。
ここでは、子どもが勉強が苦手になる背景や環境による影響を解説します。
勉強に自信を失くしている
勉強が苦手になってしまったお子さんは、自信を失くしている場合があります。
例えば、テストで思うような点数が取れなかった経験や、クラスの中で「自分だけできない」と感じる経験が積み重なると、「どうせやっても無駄」という気持ちにつながります。
また、長時間机に向かうことが苦痛だったり、集中力が続かなかったりする傾向もあります。
こうした心理的な壁は、学習意欲を大きく下げる原因になります。
家庭環境が影響していることも
家庭の雰囲気や親の声かけも、勉強への姿勢に大きな影響を与えます。
「勉強しなさい」と繰り返し言われると、子どもはプレッシャーを感じやすくなります。逆に放任状態が続くと、学習習慣が身につきにくくなります。
親が適度にサポートしている家庭では、子どもが勉強に対してポジティブな気持ちを維持しやすいです。
学年が上がると苦手が深刻化する
小学校低学年のうちは、基礎的な内容が中心なので多少つまずいてもカバーしやすいです。
しかし、学年が上がると、前の学年の内容が積み重なっていきます。特に算数は、前の学年の理解ができていないと次の単元に進めず、苦手意識が強くなります。
中学生になると定期テストや受験が現実的となり、勉強が嫌いという意識が一層深刻になることもあります。
勉強が苦手な子どもを変える!家庭でできる7つの習慣
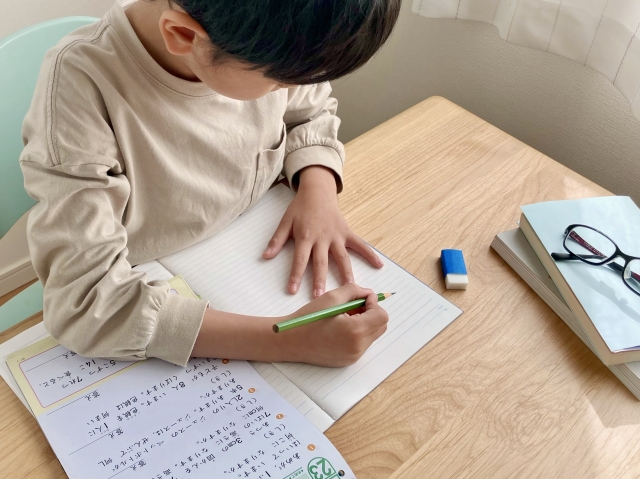 日頃の習慣を変えることで、子どもの勉強への苦手意識を和らげることができます。ここでは家庭で実践しやすい7つの習慣を紹介します。
日頃の習慣を変えることで、子どもの勉強への苦手意識を和らげることができます。ここでは家庭で実践しやすい7つの習慣を紹介します。
1、1日5分から始める
勉強が苦手な子どもには、まず短時間から取り組む習慣をつけることが大切です。1日5分だけでも机に向かう時間を確保し、少しずつ勉強の習慣を身につけます。
短時間でも毎日続けることで、「勉強することは難しくない」と感じられるようになり、集中力や継続力の基礎を育てることができます。小さな積み重ねが、自信につながります。
2、学校の宿題をペースメーカーにする
宿題は毎日の学習リズムを作る大切な目安です。時間を決めて取り組むことで、だらだらせず効率よく勉強に集中できます。
例えば、帰宅後すぐや夕食前など、固定した時間に宿題を終わらせる習慣をつけると学習リズムが安定しやすくなります。
宿題をペースメーカーとして使うことで、自然と家庭学習にも取り組む流れが作れます。
3、親子で学習計画を一緒に立てる
子どもと一緒に学習計画を立てることで、目標に向かって段階的に取り組めるようになります。
教科ごとにやるべきことを整理したり、1日の学習時間を決めたりすることで、無理なく継続する習慣が身につきます。
計画を立てる過程で親が声かけやアドバイスを行うことで、子どもが勉強に取り掛かるハードルがぐっと低くなります。
4、成功体験を積ませる
小さな成功体験を積ませることは、勉強が苦手な子どもにとって大きなモチベーションになります。
簡単な問題から取り組ませて「できた!」という達成感を得ることで、自信がつきます。成功体験は、次の学習への意欲を生み、苦手意識を和らげる効果があります。
親が子どもの頑張りを認める声かけを続けることで、より学習習慣が定着しやすくなります。
5、教科ごとに苦手を分析
教科ごとに苦手を分析し、適した方法で勉強することが大切です。
算数は計算練習で基礎を固め直す、国語は短い読解問題を繰り返すなど、できることから少しずつ慣れさせます。
教科ごとに分析することで、苦手が目に見えて改善され、子どもも達成感を得やすくなります。
6、適度にごほうびを用意する
勉強を習慣化するためには、ごほうびを効果的に使うのも良いでしょう。勉強後に10分だけゲームを許可する、シールやポイントを集めるなど、楽しみを目標にすることでやる気を引き出せます。
大切なのはごほうびの量を調整し、子どもが「頑張ったら達成感を得られる」と感じることです。ごほうびが過剰にならないようバランスを意識することがポイントです。
7、学習環境を整える
子どもが集中できる環境は、勉強の成果に直結します。
机の周りにテレビやゲーム機を置かない、スマホの電源を切る、机の上を整理しておくことなどが大切です。また、勉強に必要な教材や筆記用具をすぐ手に取れる状態にしておくことも重要です。
環境を整えることで、子どもは勉強に取り掛かりやすくなり、集中力を維持できます。
勉強が苦手な子どもに合う学習方法は?
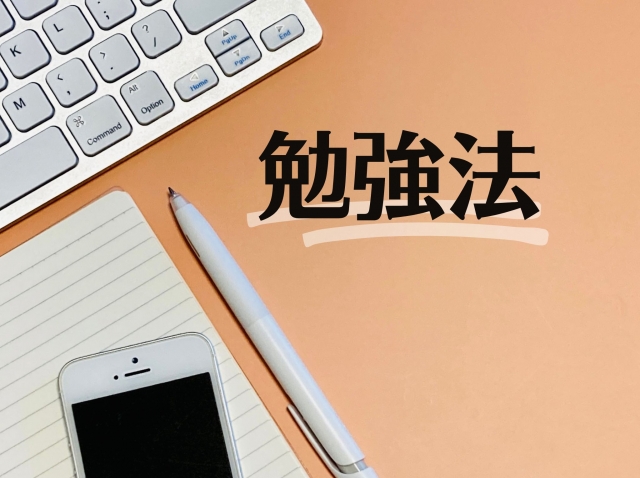 子どもに合った勉強方法を見つけることが、苦手克服の近道です。教材の選び方やサポート方法を考えてみましょう。
子どもに合った勉強方法を見つけることが、苦手克服の近道です。教材の選び方やサポート方法を考えてみましょう。
教材選びのポイント
子どもに合った教材を選ぶ際は、難易度が合っていることが重要です。簡単すぎる教材は飽きやすく、難しすぎると挫折してしまいます。
学校の教科書に沿った教材や、子どもの理解度に応じた無学年式の教材もおすすめです。
また、イラストや音声など視覚・聴覚のサポートがある教材は、勉強への興味を引きやすく、集中力を保ちやすいメリットがあります。
タブレット学習やオンライン教材の活用する
タブレット学習やオンライン教材は、勉強が苦手な子どもに取り入れやすいです。映像や音声、アニメーションを活用することで、文字だけの教材より理解しやすくなります。
問題を解くごとに正誤がすぐに分かる仕組みは、達成感を得やすく学習意欲も維持できます。さらに、ゲーム感覚で取り組める教材も多く、勉強のハードルを下げる教材として最適です。
塾や家庭教師に頼る
学校以外の学習サポートも、苦手克服には効果的です。
塾では仲間と一緒に学ぶことで刺激を受けたり、家庭教師では個別指導で理解度に合わせた勉強が可能です。
子どもの性格や学力に応じて選ぶことが重要で、強制ではなく自発的に取り組める環境を選ぶことポイントです。
塾や家庭教師による適切なサポートは、苦手意識を減らし自信の向上につながるかもしれません。
勉強が苦手な子どもの将来は大丈夫?
勉強が苦手=将来が不安と思う親は多いですが、必ずしもそうではありません。ここでは親が心配し過ぎないための視点を紹介します。
「苦手=将来の失敗」ではない
勉強が苦手だからといって将来が決まるわけではありません。学力だけが成功の指標ではなく、コミュニケーション力や創造力、問題解決能力など多様な力が求められる時代です。
苦手な科目があっても得意な分野を伸ばすことで自己肯定感を高め、将来的な選択肢を広げられます。失敗を恐れず挑戦する姿勢を育むことが、将来の成功につながります。
学力以外の強みを伸ばす
学力以外の強みを意識的に伸ばすことは、勉強が苦手な子どもにとって重要です。
スポーツ、芸術、プログラミング、協調性など、学習以外で自信をつける経験は自己肯定感を高めます。
自分の得意分野で成功体験を積むことで、勉強への苦手意識が和らぎ、勉強に取り組む意欲につながる場合があります。得意分野を伸ばすことが、将来の可能性を広げます。
親自身が心配し過ぎない
子どもの勉強が苦手だと、親も不安になりがちです。親が心配し過ぎないためには、学力だけで評価せず、子どもの成長や努力を具体的に観察することが大切です。
小さな成功や取り組みの変化を見逃さず、振り返ると良いでしょう。また、他の家庭と比較せず、子どもの個性やペースを尊重することで、親自身も穏やかに見守ることができます。
勉強が苦手な子どもには親のサポートが重要!
勉強が苦手な子どもには、心理的な要因や家庭環境、学習内容の難しさなどさまざまな背景があります。
小学生のうちは「楽しさ」を取り入れ、中学生には「自立を促すこと」を意識することが大切です。
家庭での習慣づくりや子どもに合った教材選びをすれば、勉強への苦手意識を少しずつやわらげることができます。
\勉強が苦手な子に寄り添う教材「すらら」/
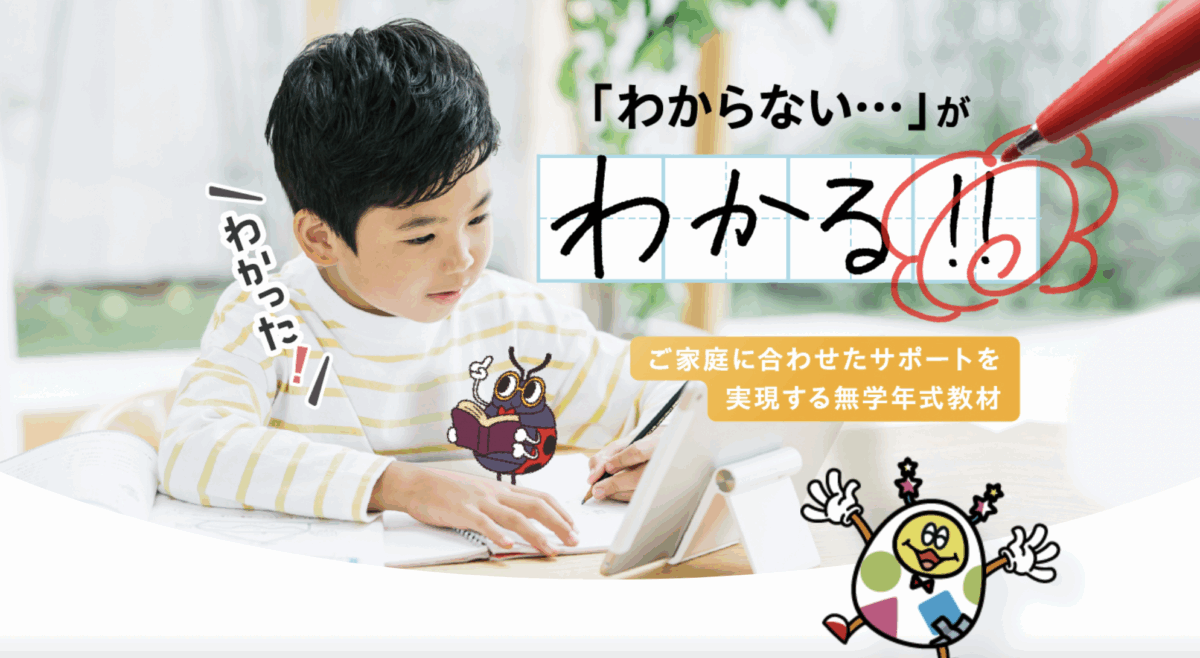 すららは無学年式の学習でいつでも自分に合った難易度の学習ができるオンライン学習教材です。
すららは無学年式の学習でいつでも自分に合った難易度の学習ができるオンライン学習教材です。
- 無学年式で自分に合った学習ができる
- ゲーム感覚で楽しく学べる
- すららコーチが個別の学習設計をサポート
- 月額8,228円(税込)〜
- 不登校でも出席扱いに
\無料の資料請求・申し込みはこちらから/
すらら公式HP>>
※この記事には一部PRが含まれます。